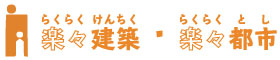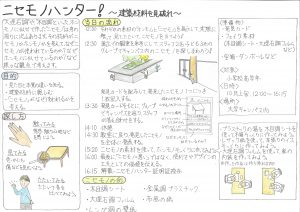第14回 子どものまち・いえワークショップ提案コンペ 審査員講評

審査委員長:山﨑健太郎(山﨑健太郎デザインワークショップ代表、工学院大学 教授)
今回初めての参加となりますが、「ワークショップ」の提案でありながら、目的・手法を明確化し、実施可能性などを考慮することは「建築」と同じであり面白いコンペだと感じました。だからこそ幅のある提案と審査員の多角的でありながらも具体的な評価基準を示して選定を進めました。昨年実施の発表でもありましたが、実施されることで得られる経験や見えてくる視座が多いため、選定されなかった提案もぜひ実施して学び取ることを推奨したいと思います。
中津秀之 (関東学院大学建築・環境学部 准教授)
ワークショップは参加者(子ども)と主催者(学生)のそれぞれに何が得られるかを考える必要があります。プログラム全体を通して、子ども目線の配慮がありながらも、子どもの発見や学びの中から設計する際のヒントに気づくことが重要です。このコンペは学生が考えるものですが、自身の設計学習にもつながります。今回建築学科以外の応募者がいなかったのは残念ですが、このコンペは建築以外の領域とコラボレーションできる可能性もあるので、是非この活動を後輩に伝えていってもらいたいです。
高木次郎(東京都立大学・都市環境科学研究科 教授)
現時点で完成度が高い提案と、素材は良いが展開が不透明な提案を比較して、将来性のある案を落とさないことを意識しました。子ども向けのワークショップでは参加者の予想外の行動への対応など柔軟な運営が必要であり、「答えを提示する」のではなく、問いかけを通じて子どもが自ら考える学びの場を提供することが重要だと思います。参加者の独自性と学びの達成感が得られるとよいと考えています。選定された案は、社会背景や課題を学ぶ機会を与えるものだと思います。成果を期待しています。
津川恵理 (ALTEMY代表)
このコンペでは、建築としての専門性がはっきりみえるもの、学会として実施するという視点をもっていることが重要だと考えています。建築的な気付きとして、正解を示す「教育」ではなく子どもが自ら感性を育み、「視座」に気づく体験の設計が大事です。昨年に引き続きの参加でしたが、実施を前提としたコンペに参加したことに敬意を感じるとともに、現代の学生には不安定な社会課題に対する「深い意志と提案力」を求めていきたいです。
中高生審査委員:伊集院子太朗 (東京都立工芸高等学校)
「子どもがどう受け取るか」をイメージして各案を評価しました。子どもは長時間集中が難しいため、建築的な学びの要素だけでなく、常に新しい刺激やワクワクする魅力的な仕掛けが必要だと考えています。その点でステンドグラスの作品は子どもに継続的な興味を引き出す仕組みができていると感じました。